<抗菌薬とは>
感染症は一般に細菌、ウイルス、寄生虫などが臓器に感染することで引き起こされます。抗菌薬はこのうち細菌にしか効かない薬です。いわゆる「風邪」の大部分はウイルス感染によるものであり「抗菌薬」は無効です。あなたが風邪を引いて医療機関を受診した時には、抗菌薬が必要でない可能性が非常に高いですが、未だに風邪・急性上気道炎に抗菌薬を処方する医師が後を絶ちません。
<抗菌薬の不適切な使用とは>
抗菌薬の不適切な使用は医療費の無駄を増やしたり、耐性菌の増やしたり、患者を不必要な副作用のリスクに晒す可能性が指摘されています。
実際に米国で急性上気道炎及び気管支炎に処方される抗菌薬の50%は不必要な抗菌薬処方と言われているそうです。日本の厚生労働省が出している指針においても、感冒(風邪)に対して抗菌薬投与は基本的に必要ないとのスタンスを示しています。
<抗菌薬処方に対する行動介入試験>
抗菌薬の処方は医師が権限を持っています。そのため医師に対して抗菌薬の不適切使用を抑制するための介入が求められています。
Danielら(2016)の研究で以下のような行動介入試験が18ヶ月間行われました。
①コントロール群
抗菌薬の適正使用に関するガイドライン配布と教育プログラムを提供するという古典的な介入。
②代替案提示群
抗菌薬を処方しようとすると、画面上で抗菌薬以外の対症療法がおすすめされるという介入。
③抗菌薬仕様の際に理由を入力する群
急性上気道炎に対して抗菌薬を処方しようとすると、抗菌薬を使用する理由を入力しなければいけないという介入。
④抗菌薬の不適切利用の少ない医師との比較データ提示群
抗菌薬の不適切投与が少ない医師との抗菌薬処方率の比較データが送られてくるという介入。
この介入の結果、
①コントロール群と比較して、
③抗菌薬仕様の際に理由を入力する群と④抗菌薬の不適切利用の少ない医師との比較データ提示群では抗菌薬の処方が減る(それぞれ-5%, -7%)というデータが示されました。
もっとも①コントロール群における教育でも11%程度抗菌薬処方が減っていることから教育介入の重要性も示唆されます。
③抗菌薬仕様の際に理由を入力する群というのはまさにChanging Default Opition(初期設定を変える)というNudgeを応用したもので、抗菌薬投与に理由付けを求めることで「抗菌薬を投与しない」ことがDefaultになるように工夫されています。
④抗菌薬の不適切利用の少ない医師との比較データ提示群はPeer Pressure, Feed backの応用で同僚との比較や、周囲からのプレッシャーによって行動をNudgeしようという戦略です。医師はプライドの高い生き物なので、数字でリアルにフィードバックを受けて比較されると燃えるのかもしれません
一方で②が有意な介入とならなかったのは、他の選択肢を提示されたところでDefaultである「抗菌薬処方」に、多くの医師の意思決定が引きずられたものと考えられます。
もちろん有意差がないことが差がないことの証明にはなりませんが、忙しい臨床現場の中で、他の治療方法をおすすめするポップアップが出てきてもすぐさま消してしまうような気がします。
<フォローアップ研究>
ちなみにこの研究には18ヶ月間の介入を終えたあとにもフォローアップ期間が設けられていました。介入終了後12ヶ月間の抗菌薬処方率を調べたところ、コントロール群よりも低い処方率となったのは④抗菌薬の不適切利用の少ない医師との比較データ提示群のみでした。
しかし、一度電子カルテに組み込まれた介入をあえてやめる意味がよくわかりません。システムの維持費もおそらくほとんどかからないはずです。また、医療現場では人材の入れ替わりも非常に激しいため、このような介入を常に続ける必要があると私は考えます。
<ちなみに>
私がこれまで過去に勤務した病院では、広域スペクトラム抗菌薬(より多くの菌種に作用する抗菌薬)の使用に際して届け出が必要な病院が複数ありました。不必要な抗菌薬使用をへらすと同時に、広域スペクトラム抗菌薬投与を受けている患者の状態を、感染症内科専門医が後方でモニタリングできるようにするための制度です。これも立派なNudgeだと思います。
<まとめ>
・風邪(ウイルス感染症)に対する抗菌薬使用は不適切。
・Changing Default OptionやPeer Pressureといった戦略が医師の処方行動をNudgeできる可能性がある。
・介入後は効果が薄れたようだが、実務ではそもそも介入をやめる必要はない。
<参考文献>
1)1つ目の介入研究 Daniella et al (2016)
2)フォローアップ研究 Jeffrey et al (2017)



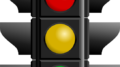
コメント